👉この記事のポイント
- エンジニア採用基準とは?
エンジニアにおける採用基準とは自社が求める人物像・スキルセットを明文化した評価の基準です。
- 基準策定の具体的手順
エンジニア採用基準は、目的の明文化から現場との連携、要件定義、市場分析、求人票への反映まで段階的に設計することが重要です。
- 改善ポイント
採用基準は効果測定や市場変化に応じて見直しが必要です。面接官トレーニングで基準の精度と運用力を高めましょう。
関連動画:なぜエンジニア採用は失敗するのか?母集団形成から内定までの落とし穴
エンジニア採用における採用基準とは
エンジニアの採用活動を成功させるためには、明確な基準に基づいた評価・選考が不可欠です。
特に技術職であるエンジニアは、業務内容が専門的で、求められる資質も多岐にわたるため、感覚的な判断だけではミスマッチを招きやすくなります。
この章では、まず「採用基準」とは何か、そしてそれがなぜエンジニア採用において重要なのかを明確にしていきます。
エンジニアにおける採用基準の概要
エンジニアにおける採用基準とは、自社が求める人物像・スキルセットを明文化した評価の基準です。
単なるスキルチェックにとどまらず、「どのような人を、どの基準で採用すべきか」を組織全体で共通認識として持つための指針といえます。
採用基準があることで、候補者を公平に評価できるだけでなく、求人設計・面接・内定判断まで一貫した流れで運用することが可能になります。
また、候補者との相互理解を深め、入社後のミスマッチを防ぐ上でも大きな役割を果たします。
エンジニア職において採用基準が重要な理由
エンジニアという職種は、他の職種と比べて技術領域が多岐にわたり、必要なスキルや人物像が企業やプロジェクトごとに大きく異なります。
そのため、あいまいな採用方針のままでは、面接や選考において判断軸がばらつきやすくなります。
採用基準が明確であれば、選考プロセスにおける評価の一貫性を保つことができ、結果として入社後の定着率や活躍率の向上にもつながります。
また、求人票やスカウトなどの候補者接点でも一貫したメッセージを発信できるため、採用全体の質とスピードが大きく向上します。
採用基準を策定するメリット
採用基準を策定することで、選考の精度やスピード、そして採用ブランディングにも大きな効果が得られます。ここでは、採用基準を明文化することで得られる主なメリットについて紹介します。
- 客観的なスキル評価で採用精度が向上する
- 磨かれた求人情報で求職者にアピールができる
- 効率的に採用活動を行える
この3点について詳しく解説していきます。
客観的なスキル評価で採用精度が向上する
エンジニアの採用にあたっては、特にハードスキルの評価が最も重要です。
そのため、
- プログラミング言語(例:Python, Java)
- フレームワーク(例:Rails, Django)
- ライブラリ・パッケージ(例:Selenium, TensorFlow)
- ツールの使用経験(例:Git, Docker)
- サーバー・環境(例:AWS, Azure)
など、技術的なスキルを網羅的に評価することが求められます。
採用基準を正しく運用することにより、評価のブレを抑え、より客観的な判断が可能になります。一律の客観的な評価を求職者に出せることで採用精度が向上し、採用の質が高まるでしょう。
具体的な評価手法としては、たとえばコーディングテストを実施し実務レベルの技術を確認したり、ペアプログラミングを通じてコミュニケーション力や問題解決のアプローチを見極めたりする方法があります。また、システム設計課題によって論理的思考力を評価したり、ポートフォリオを通してこれまでの開発経験やスキルの深さを可視化することも有効です。
磨かれた求人情報で求職者にアピールができる
企業が設定する採用基準は、単に応募者を選別するためだけのものではありません。磨き上げられた採用基準は、求人情報そのものの質を高め、企業の魅力を効果的に伝えるための重要なツールとなります。
たとえば、「フロントエンドでの開発経験がある方募集中」といった表現と、「フロントエンドでの3年以上の実務経験、Reactを使用した1年以上の開発経験」といった表現では、求人情報の解像度に大きな差があります。数字や具体的なツール名を含めるだけで、求職者が受け取る情報の鮮明さは格段に向上します。
このように採用基準を言語化・明文化することで、企業としての期待や価値観が求人情報に落とし込まれ、よりマッチした人材からの応募を促すことが可能になります。また、採用基準は求人票に表れるだけでなく、自社のビジョンや理念、求める人材像そのものの明文化にも繋がります。結果として、採用基準を通じて企業の魅力を伝えることができ、優秀な人材を引き寄せる強力な武器になるのです。
効率的に採用活動を行える
採用基準を策定することで、効率的に採用活動を行うことに繋がります。理由は主に以下の2点あります。
- 候補者の判断スピードが速まるから
- 採用母集団の質が上がり、自社にマッチしない人材を排除できるから
まず、明確な基準があることによって、候補者のスクリーニングや面接プロセスが迅速かつ効率的になります。採用基準が曖昧だと、客観的な判断ではなく、主観で判断することになります。主観で判断する場合、どの候補者が最適であるかの判断に時間がかかってしまいます。その結果、選考プロセスに遅延が生じるのです。よって、採用基準を明確にすることは採用の効率化につながるといえます。
また、採用母集団の質が上がるという点も挙げられます。採用基準に合致する候補者を迅速に見つけることができるため、不適切な候補者に割く時間を割くことができ、結果として採用活動の効率化に繋がります。
採用基準設定に役立つ3つのフレームワーク
採用基準をより精度高く構築するには、フレームワークの活用が効果的です。ここでは、採用現場で広く活用されている3つの代表的なフレームワークを紹介します。
- Must / Want
- STARモデル
- ICEスコアリング
この3つのフレームワークの特徴と活用方法について解説していきます。
| フレームワーク | 概要 | 活用方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| Must / Want | 必須要件(Must)と望ましい要件(Want)を分類し、採用基準を明確化。 | 必須要件を設定し、それを満たす候補者を選定。 | 基準が明確になり、効率的に選定できる。 | 必須要件を厳しくすると候補者が減る。 |
| STARモデル | 候補者の過去の経験を状況・課題・行動・結果で評価。 | 面接でSTARの順に質問し、具体的な実績を確認。 | 客観的な評価が可能で、実務能力を把握しやすい。 | 準備された回答により、実力を見抜けない可能性。 |
| ICEスコアリング | 影響力・確信度・適応度を数値化し、定量的に評価。 | I・C・Eをスコア化し、合計値で比較。 | 数値による比較ができ、統一基準を持ちやすい。 | スコア設定次第でバランスを欠くリスクがある。 |
Must / Want
採用基準を「必須要件(Must)」と「望ましい要件(Want)」に分けるシンプルなフレームワークです。
活用方法
- Must(必須要件): 採用候補者が最低限満たすべき要件
- 例: 営業経験3年以上、基本的なPCスキル、法人営業経験 など
- Want(望ましい要件): あればより良いスキル・経験
- 例: SaaS業界での営業経験、マネジメント経験、英語力 など
このフレームワークの最大の利点は、そのシンプルさにあります。必須要件が明確になることで、採用プロセスが効率化され、基準を満たさない応募者を早い段階で除外できます。一方で、必須要件を厳しくしすぎると候補者が極端に少なくなるリスクがあります。また、望ましい要件を増やしすぎると採用ハードルが高くなり、結果として適切な人材を逃してしまう可能性もあります。
STARモデル
候補者のスキルや経験を具体的な行動ベースで評価するフレームワークです。
面接で候補者の過去の経験を確認する際に使用します。
- S(Situation / 状況): どんな状況だったか?
- T(Task / 課題): どんな課題・役割があったか?
- A(Action / 行動): どのように対処したか?
- R(Result / 結果): どのような成果を出したか?
このフレームワークを活用すると、候補者の経験を具体的に掘り下げることができ、客観的な評価が可能になります。過去の行動を分析することで、その人材の実務能力を正確に測ることができる点も大きなメリットです。しかし、候補者が適切なエピソードを持っていない場合、評価が難しくなります。また、候補者が事前に準備したストーリーを話すだけになってしまうと、実際の能力を正しく判断できなくなることもあります。
ICEスコアリング
候補者の能力を数値化し、客観的に評価するフレームワークです。
各候補者を以下の3つの基準で評価し、合計スコアを比較します。
- I(Impact / 影響力): その人材が組織に与える影響度
- C(Confidence / 確信度): 採用時の成功確率(どれだけ確実に成果を出せるか)
- E(Ease / 適応のしやすさ): 企業文化やチームへのフィット感
このフレームワークの大きな利点は、感覚的な評価を避け、定量的に候補者を比較できる点です。スコアによる評価は、採用チーム内での共通認識を持ちやすくし、意思決定をスムーズに進めるのに役立ちます。しかし、評価項目の重み付けを適切に行わないと、スコアのバランスが偏り、候補者の特性を正しく評価できなくなることがあります。また、スコアの算出方法によっては、個別の強みや特徴を見落としてしまうリスクもあります。
【5ステップ】エンジニア採用基準の策定方法
エンジニア採用を成功させるには、属人的な判断ではなく、明確かつ再現性のある採用基準の設計が不可欠です。
そのためには、段階的に要件を洗い出し、自社の採用目的と市場環境を踏まえて練り上げていく必要があります。
ここでは、エンジニア採用基準をゼロから設計するための5つのステップをご紹介します。
- 採用活動の目的を明文化する
- 現場メンバーと役割要件をすり合わせる
- MUST/WANT/人物像を定義する
- 採用市場・競合分析を行う
- 求人票に具体的な採用基準を記載する
それぞれについて詳しく解説します。
採用活動の目的を明文化する
採用基準を策定する前に、まず「なぜこの採用を行うのか」という目的を明文化することが出発点です。
事業成長に伴う体制強化なのか、特定領域のスキル補完なのか、背景によって求める人物像も変わります。
目的が曖昧なまま採用活動を始めると、評価軸がブレやすく、社内の合意形成も難しくなります。
そのため、目的を言語化し、経営層・現場・人事で共有しておくことが、全体の基準設計をスムーズに進める鍵になります。
現場メンバーと役割要件をすり合わせる
採用基準は人事部門だけで策定するものではありません。
実際にエンジニアと関わる現場メンバーとのすり合わせを行い、業務内容・役割・必要スキルを具体的に洗い出すことが必要です。
現場を巻き込むことで、実務に即した基準を設けることができ、入社後のギャップを防げます。
また、現場も納得感を持って採用に関与できるため、組織全体での採用の質が高まります。
MUST/WANT/人物像を定義する
基準策定の中心は、「絶対に必要な要素(MUST)」「あると望ましい要素(WANT)」「理想的な人物像」の3つを明確に定義することです。
MUSTは評価において譲れない最低ラインであり、ここを満たさない候補者は通過させるべきではありません。
一方、WANTは差別化要素として、候補者の強みを見極める観点です。
さらに、スキルだけでなく、価値観や志向性も含めた人物像を言語化しておくことで、カルチャーフィットの判断にも役立ちます。
採用市場・競合分析を行う
自社にとって理想的な基準を定めたとしても、それが採用市場に存在しない人材像であれば意味がありません。
そのため、外部環境の分析も欠かせない要素となります。
具体的には、求人媒体や競合他社の採用条件を調査し、現実的な条件設定に落とし込むことが重要です。
市場と自社のギャップを把握して調整することで、実現可能性の高い採用活動が行えるようになります。
求人票に具体的な採用基準を記載する
最後に、設計した採用基準を求人票へと反映させましょう。
求人票は候補者との最初の接点であり、曖昧な表現ではなく、具体的な要件や求める人物像を明記することで、応募の質と量の両面が向上します。
また、MUST・WANT要件や業務イメージが明確に示されていれば、候補者自身がマッチ度を自己判断しやすくなり、選考の効率も高まります。
採用基準の言語化は求人票で完結させる意識で仕上げましょう。
【注意】エンジニア採用基準策定で失敗しがちなポイント
エンジニア採用基準を設けることは、採用活動の精度を高めるうえで欠かせません。
しかし、基準の内容や決め方を誤ると、採用がうまくいかないばかりか、社内に混乱を生む要因にもなります。
ここでは、企業の人事担当者が陥りがちな失敗ポイントを5つ紹介します。
- 経営・人事主導で現場視点が欠如している
- 基準が理想論になっている
- ソフトスキルの定義が曖昧になっている
- 採用市場を無視した設定になっている
- 更新・改善されないまま放置されている
対策を事前に把握し、効果的な基準策定を目指しましょう。
経営・人事主導で現場視点が欠如している
エンジニア採用におけるよくある誤りが、人事や経営層だけで採用基準を設計してしまうケースです。
実務を担うエンジニアチームの意見を反映しないまま要件を決定すると、現場ニーズとズレが生じやすくなります。
その結果、実際の開発に必要のない技術や、非現実的なスキルレベルを求めてしまう事態が起こります。
基準策定では、必ず現場エンジニアの視点を取り入れ、採用後にギャップが出ないようにすることが重要です。
基準が理想論になっている
「できるだけ優秀な人材を採用したい」という気持ちが先行すると、採用基準が理想像に偏ってしまいます。
幅広いスキルセットや即戦力性をすべての候補者に求めると、現実には該当者がほとんどいなくなり、採用難に陥ります。
採用基準は、理想と現実のバランスをとることがカギです。
自社にとって本当に必要な条件をMUST要件として明確にし、余裕があれば望ましいとされるWANT要件を追加で記載する形にしましょう。
ソフトスキルの定義が曖昧になっている
エンジニア採用では、技術力だけでなくソフトスキルの評価も欠かせません。
しかし「コミュニケーション力」や「協調性」などの言葉だけでは、評価者によって判断が大きく異なる恐れがあります。
このような抽象的な表現のまま採用基準に組み込んでしまうと、面接官ごとに基準がブレてしまい、採用の再現性が低下します。
そのため、ソフトスキルは具体的な行動や状況をもとに定義し、明確な評価軸を設けることが求められます。
採用市場を無視した設定になっている
自社の理想や都合だけで採用基準を作ってしまうと、実際の採用市場と大きく乖離してしまいます。
特にエンジニア職は売り手市場が続いており、候補者は複数のオファーを比較検討しています。
そのため、市場での相場感や競合他社の動向を把握しないまま基準を設けると、応募が集まらず採用が難航します。
定量的なデータや求人事例をもとに、市場と折り合いのつく基準を設定することが不可欠です。
更新・改善されないまま放置されている
一度作った採用基準をそのまま使い続けている企業も少なくありません。
しかし、技術トレンドや事業内容、社内の開発体制は日々変化しており、採用基準もそれに合わせて見直す必要があります。
過去に策定したまま放置されている基準では、現在の採用活動に合わなくなっている可能性が高くなります。
採用後の振り返りやデータ分析を通じて、基準の妥当性を定期的にチェック・改善する体制を整えることが重要です。
未経験エンジニア採用基準設定のポイント3選
未経験人材を採用する際には、実務経験よりも将来の可能性や企業文化への適応力といったソフト面が重視されます。以下の3点を基準設計に取り入れることで、より適切な人材を見極めることが可能です。
- ポテンシャル評価を軸にする
- カルチャーフィットを明文化する
- 最低限のスキル要件は明示する
それぞれについて詳しく解説します。
ポテンシャル評価を軸にする
未経験層の採用においては、実務経験の有無ではなく、成長するポテンシャルを見極めることが鍵となります。評価項目としては、独学での学習歴、プログラミングスクールでの課題提出状況、ポートフォリオの有無などが挙げられます。さらに、GitHubでの活動やQiita投稿など、技術に対する主体的な取り組みが見えると、成長意欲の高さが評価できます。「深く知っている」よりも「どう向き合っているか」を重視した評価軸が有効です。
カルチャーフィットを明文化する
実務経験がない未経験者にとって、組織文化との適合度は成果を出す上で極めて重要です。自社がどのような価値観を持っているか、例えば「自律性を重んじる」「チームワーク重視」などを明文化し、選考時に候補者の志向とすり合わせる必要があります。これにより、入社後の定着率向上やオンボーディングの効率化につながります。
最低限のスキル要件は明示する
「未経験=完全な初心者」というわけではありません。基礎的な技術スキルの習得は最低条件として提示することが、選考の質を担保するうえで欠かせません。例えば「HTML/CSSの基本操作ができる」「Gitでの簡単なバージョン管理が可能」といったラインを設けることで、スクリーニングがしやすくなり、教育コストの最適化にもつながります。
経験エンジニア採用基準設定のポイント3選
経験者採用では、即戦力性や業務成果の再現性が評価の中心となります。以下の3つの視点を採用基準に盛り込むことで、配属後のミスマッチを防ぎ、高いパフォーマンスが期待できる人材を確保できます。
- 実務スキルを具体的に定義する
- 開発スタイルとの親和性を評価に含める
- 成果の再現性を重視する
それぞれについて詳しく解説します。
実務スキルを具体的に定義する
経験者のスキル評価では、表面的な技術名ではなく、具体的な業務経験に基づいたスキル定義が重要です。使用言語やフレームワークだけでなく、「何の目的で、どう使ったか」を面接前に把握できるような基準設定が求められます。例えば「Reactを使ったSPA開発経験」「AWS上でのインフラ構築・運用経験」など、業務内容に即した記述があると精度の高い選考が可能です。
開発スタイルとの親和性を評価に含める
どれほどスキルが高くても、自社の開発手法と合わない場合は成果が上がりにくくなります。たとえばアジャイルやスクラムといった手法に慣れているか、コードレビュー文化に馴染めるかといった点も重要な評価軸になります。自社の開発スタイルを明文化し、それに近い環境での経験がある人材を優先的に評価する仕組みが効果的です。
成果の再現性を重視する
実績があっても、それがたまたまの成果では意味がありません。再現性のある成功体験を持っているかを確認するために、STAR法(状況・課題・行動・結果)を用いた深掘り面接が有効です。このような手法を取り入れることで、他社での成果が自社でも再現されうるかを見極めやすくなります。属人的な成功ではなく、論理的なプロセスに基づいた成果を重視しましょう。
採用フェーズごとの基準運用方法
採用基準は作るだけでは意味がなく、各選考フェーズで適切に運用することが求められます。ここでは、書類選考から最終面接までのプロセスにおける基準の使い分け方を紹介します。
- 書類選考:基本的な要件重視
- 技術試験:実務の技術重視
- 面接:チームフィット重視
- 最終面接:総合的な最終判断
上記4つのフェーズごとに基準運用のポイントを解説します。
書類選考:基本的な要件重視
書類選考では、最低限の必須スキルや経験を有しているかを確認します。
また、志望動機などで明らかに自社の内容から外れている場合は不合格とするのが良いでしょう。
基本的に書類選考では人材のハード面の最低要件であるMUSTを重視し、満たしている人材は通過させるようにしましょう。ソフト面での違和感は次の技術試験や面接の段階で通過の判断を行うことができるため、通過人数を確保することを優先しましょう。
技術試験:実務の技術重視
技術試験はエンジニアが中心となることが重要です。募集ポジションに応じてコーディングテストやシステム設計の試験を課します。
ここでは、
- 経歴と実務スキルのギャップ
- WANTスキル
- エンジニアとしてのソフトスキルの充実度
を確認することが求められます。
ここでは、実際の現場で働くことを想定した評価が重要です。求職者が自社の現場で働く時にどの様な付加価値が出せるか、必要な業務を担うことへの評価が重視されます。この技術試験でスキルが自社で補えないほど不足していると考えられた場合はお見送りしましょう。
また、書類選考で評価できないチームフィットやコミュニケーション能力も試験を通じて評価しましょう。
面接:チームフィット重視
この面接では技術スキルの評価ではなく、チームフィット力や企業への適合性の評価が中心となります。
技術試験で評価した部分も併せて、企業カルチャーやチームとの適合性を評価し、価値観の共有を行います。
面接では基準を作成する際に決定したエンジニアに必要なソフトスキルについても質問を通じて見極めることが必要です。具体的にはSTARメソッド(状況、タスク、行動、結果)を使用した事例質問を行うことができると良いでしょう。
ソフトスキルと企業への適合性を評価することで選考の通過の判断を行います。面接官が求職者と話しやすいことやコミュニケーション能力が高いことを中心に評価することは間違いです。必ず採用基準の設定を忠実に守り、選考通過の判断を行いましょう。
最終面接:総合的な最終判断
最終面接は経営視点からの適正評価や企業理解の評価を行う段階です。また、他の応募者の選考状況も踏まえて総合的に求職者に内定の判断を行います。
特に自社が採用ブランディングを行った部分に対してどのように求職者が考えているかやオファー内容と求職者の思考性に相違がないかにも着目すべきです。
総合的な判断をおこなうため、他の候補者と比較する事が重要です。候補者のメリット・デメリットを深堀りして把握することや採用時の評価と入社後のパフォーマンスの関係等を総合的に判断することが必要になるでしょう。
採用基準の改善ポイント
一度作成した採用基準も、時代や市場の変化に合わせて継続的に改善していく必要があります。ここでは、採用基準の効果測定と改善につなげるためのポイントを紹介します。
- 現場の声をフェーズ毎に収集
- 効果測定による成果の数値化
- 市場分析によるエンジニア相場のキャッチアップ
- 基準の最適化基づいた面接官トレーニング
この4つの視点から、採用基準の改善サイクルについて解説していきます。
現場の声をフェーズ毎に収集
採用フェーズごとに、現在運用している基準での困難なポイントを面接等の評価シートを元に収集することが必要です。応募数や選考段階ごとの通過率と評価シートの内容を照らし合わせ、必要な人材がはじき出されていないかを確認することが求められます。
特に、応募数が少ない、選考通過率が悪い場合には、MUSTに設定したスキルを見直す必要があります。必須の要素や条件が厳しいために、応募してくれない、選考を通過できないことが想定されるからです。
面接官が好感を抱いたポイントがあったにもかかわらず、選考を通過できなかった理由などを分析し、必要があれば改善することが求められます。
効果測定による成果の数値化
採用における情報を定量化することで客観的にレビューすることができます。
採用段階では、採用コスト、採用期間、離職率などを指標として設定し、目標達成度を測定します。また、入社後の段階では新入社員のオンボーディング状況、開発案件への貢献度、パフォーマンスなどを評価します。
これらの指標に基づいて、採用基準が成果にどのような影響を与えているかを分析し、改善点を見つけ出します。また、選考時の評価と入社後のパフォーマンスを分析することで、活躍する人材の特徴や採用基準との関連性を調査することができ、自社の採用方向性を改善するきっかけになります。
市場分析によるエンジニア相場のキャッチアップ
IT業界においてトレンドの変化は非常に激しい状態です。数年前であればビックデータの分析がトレンドでしたが、現在はその先の分野である、生成AIがトレンドとなっています。このトレンドの変化により必要な人材の質や目的も変化しています。
そのため、求人情報サイトや転職エージェントの情報などを収集し、類似職種におけるスキルや経験、給与水準などの調査が定期的に必要です。また、合わせて競合企業の求人情報や採用活動に関する情報を収集し、自社の採用基準と比較分析することが必須となるでしょう。
自社の採用基準が市場の中で競争力を保持し続けることが非常に重要です。
基準の最適化基づいた面接官トレーニング
ここまでの情報を統合し、面接官のトレーニングも行う必要があります。
特に、「WANTスキルの変更点」や「選考時の評価と入社後のパフォーマンスとの関連分析結果」、「採用現場でのフィードバック」を中心に改善する必要があります。
採用基準が正しく適用されているかの判断に際して、現場エンジニアの協力が必要です。定期的な模擬面接の実施やフィードバックドキュメントの共有による相互的なチェックが採用を活性化させるでしょう。
面接官トレーニングの目的や背景とは?実践方法や必須スキルまで徹底解説!
エンジニア採用基準についてよくある質問(FAQ)
エンジニア採用基準についてよくある質問をまとめました。
スキル基準ってどうやって決めればいい?
まずは「現場でどんな技術・タスクに取り組むか」を棚卸しし、それに必要なスキルを洗い出すのが基本です。
流行の言語やツールよりも、実務に必要な技術との整合性を重視することが大切です。
中途と新卒で採用基準は変えるべき?
はい、明確に分けるべきです。中途は実績や即戦力性を、新卒はポテンシャルや価値観の一致を重視します。
基準を分けることで、選考時の評価ブレを防ぎやすくなります。
カルチャーフィットってどう見極める?
面接時に「働き方の志向」や「チームでの役割意識」「意思決定の傾向」などを具体例をもとに聞き出すのが有効です。
特にリモート志向の強さや柔軟な学習姿勢は、企業文化との相性に大きく関わります。
採用基準は一度作ったら終わり?
継続的な見直しが必要です。
実際に採用した人材が活躍できているかを振り返り、現場の声や事業フェーズの変化をもとに、定期的にアップデートすることが理想です。
まとめ
エンジニアの採用基準について、基準の作成方法・運用方法を実際の事例を交えながらご紹介しました。
エンジニアの採用業務は、企業の技術力の向上に直結する重要な業務です。技術力の向上が企業の生産性や品質の向上に影響するため、エンジニア採用業務にお悩みの方は採用基準の見直し、作成、運用を行ってみてはいかがでしょうか?
採用が難しいと感じている方は株式会社uloqo(旧株式会社プロジェクトHRソリューションズ)お任せください!
▼サービスに関するお問い合わせはこちらから

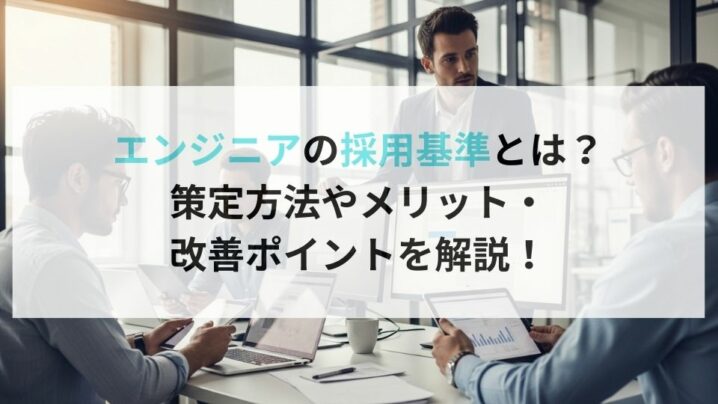


のコピー-25-300x200.jpg?x82548)

-300x200.jpg?x82548)


サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg?x82548)

