昨今のテレワークの需要の拡大により、成果物で評価されるジョブ型雇用についての関心が高まっています。そこで今回は、ジョブ型雇用のメリット・デメリットや導入企業例を紹介します。
ジョブ型雇用とは
ジョブ型雇用は仕事の範囲を明確に指定して採用する雇用形態です。人に仕事を割り振るのではなく、仕事に人を割り振ります。職種を限定して募集し、その職務を遂行できるスキルを持った人材を採用します。その結果、それぞれの職種で専門性を高めることが可能です。欧米諸国では、ジョブ型雇用が一般的な雇用方法となっています。
この雇用形態では、年齢や学歴、職歴などに左右されずに個人のスキルを重視します。業務に必要なスキルを持っていることを前提としているため、入社後の研修がなく、個人の業務外の自己学習が必要です。
一つの会社で一生働き続けるのではなく、スキルを磨いてより好待遇な職場を目指します。転職のための障害が少ないため様々な企業でキャリアを積んでいくのが一般的な形です。
また、採用や人事評価の際、職務記述書(ジョブディスクリプション)というものを設定しなければなりません。これは職務や職種によって必要とされる業務スキルと業務内容などを網羅的に記述した書面です。職務記述書を設定することで専門的人材の採用を目指します。
さらに、能力によって取り組む業務が変わり報酬も変わるので、ジョブ型雇用は成果主義の一面もあります。
【関連記事】ジョブディスクリプションとは?書き方や具体的な項目例を説明します!
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違いは?
メンバーシップ型雇用とは
ジョブ型雇用と比較されるのはメンバーシップ型雇用と呼ばれる方法です。これは、終身雇用や年功序列の報酬体系など、高度経済成長期以来、日本企業で続けられてきた雇用形態です。メンバーシップ型雇用では新卒社員を総合職として一斉採用します。会社のメンバーとして雇用し、様々な業務に関わることによって経験を積ませ、会社を支える人材を育成します。
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の比較
ジョブ型雇用の特徴とメンバーシップ型雇用の特徴を下表で比べました。
| ジョブ型雇用 | メンバーシップ型雇用 | |
| 仕事の領域 | 事前に確定されており、一つの職種に専念できる。 | 幅広い分野に携わり、会社の都合で変化する。 |
| 報酬 | 働く業種やスキル、成果に依存する。 | 年齢や勤続年数に大きな影響を受ける。 |
| 採用傾向 | 経験やスキルのある人材を雇う中途採用。 | 新卒一括採用。 |
| 教育制度 | 無し。自己分析と学習が必須。 | 会社での手厚い教育研修がある。 |
| 人材の流失 | しやすい。能力の高い人材ほど高い報酬がある場所に向かうことができるため。 | しにくい。勤続年数を積み重ねるほど報酬が上がっていくため。 |
| 転勤の有無 | 職務記述書で定められていない限りない。 | 会社の都合で転勤する必要がある。 |
| 職の喪失 | 時勢や景気により職務がなくなる場合がある。 | ジョブローテーションにより雇用を確保することができる。終身雇用が原則。 |
経団連がジョブ型雇用を推奨した?
ジョブ型雇用への関心が高まった背景として、2020年に日本経済団体連合会(経団連)の当時の会長・中西宏明氏が「1つの会社でキャリアを積んでいく日本型の雇用を見直すべき」と発言したことがあります。経団連の会長が、大手企業が行ってきた新卒一括採用やメンバーシップ型雇用を否定するような発言をしたことは大きな話題になりました。
また、新型コロナの流行によりテレワークの機会が増えると、従業員の姿が見えない中で成果をあげる人材マネジメントが必要だとされました。そこで、成果物が分かりやすいテレワークとの相性が良いジョブ型雇用に注目が集まったのです。
ジョブ型雇用を導入するメリット
専門性を高めることができる
単一の業務にスキルを持った人材を充てるため、従業員は自分の得意な一つの分野に集中しスキルを磨くことが可能です。そのため専門性が高まり、より高度な作業ができるようになります。
リモートワーク・テレワークとの相性がいい
テレワークでは労働時間の管理や人事評価が難しい面があります。そこで、仕事の内容に沿って採用するジョブ型に転換して、仕事そのものの成果に着目した評価の仕組みに変えることが好ましいでしょう。リモートワークやテレワークは成果物がハッキリと出るため定量的な評価が容易です。また、一人ひとりにジョブが割り振られているジョブ型雇用はリモートであっても自身のやるべきことが分かりやすいです。
同一労働同一賃金を実現できる
ジョブ型雇用であれば、事前に業務と成果に対応する賃金が決定しています。大きな成果を出しているはずなのに、勤続年数の差によって給料が釣り合わなかったり、大した仕事をしていなくても多額の報酬が出るということはありません。
ジョブ型雇用を導入するデメリット
会社都合の異動やほかの業務を任せることができない
ジョブ型雇用では従業員は業務記述書に沿って働くため、事前に決めた業務以外のことをさせることができません。1人の社員がする仕事が決まってしまい、柔軟に対応していくことが難しくなります。
才能のある人材が定着しない
同業種内での転職がしやすくなります。従来の雇用形態では終身雇用が基本でしたが、ジョブ型雇用では能力があれば、より好待遇な場所へと転職していくことが容易です。というのも業務に関するスキルを重視しており、前職の勤続年数や年齢が不利に働くことが少ないためです。
新卒の社員が活躍しにくい
ジョブ型雇用では専門的なスキルが求められるため、中途採用が優先されることになります。メンバーシップ型雇用では丁寧な教育研修があるのに対して、ジョブ型雇用では積極的な自己学習を前提とするため、経験のない新卒社員は不利です。
職がなくなる可能性がある
景気や時勢により特定の業務自体がなくなることがあり、その際にジョブローテーションや職務転換といった選択肢が存在しないため退職につながることがあります。一つの職務に就くことを前提として採用しており、その職務自体がなくなると解雇となってしまうかもしれません。
日立や富士通、KDDIなどジョブ型雇用を取り入れた企業の事例をご紹介します
日立

日立は、能動的に活躍できる人を増やして会社の成長へとつなげていくために、ジョブ型雇用を導入しています。海外子会社の21万人に加え、2022年7月までには国内で働く3万人に適用しており、2024年までに国内子会社の16万人にも拡大する予定です。
「従業員は自分の目指すキャリアを明確にする。会社は職務や必要なスキルなどを明確にし、その仕事を担える人を、年齢や属性にかかわらず本人の意欲や能力に応じて登用していく」と推進プロジェクトを率いる岩田幸大企画グループ長は話しています(2020年)。
日立の職務記述書は300~400種類存在し、その全てにポジション名やミッションと役割、必要な能力・スキル・資格・経験を記載し、能力と意欲に応じた「適所適材」の配置を目指しています。
富士通
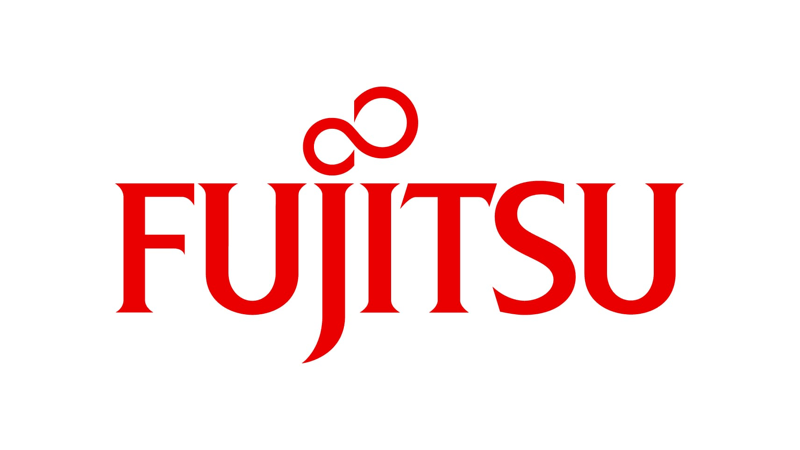
2020年4月に富士通株式会社は幹部社員約1万5,000人を対象にジョブ型雇用制度を導入すると発表しました。それに加え、2022年4月には一般社員4万5,000人に導入し、すべての階層を対象にしました。
富士通が導入したジョブ型雇用の特徴は、7段階の格付けです。格付けは全世界共通であり、。職責の大きさや重要性等を格付けし、報酬に反映させます。
社員一人ひとりが高い意欲を持ち価値の創出を目指し、成長することを目的としています。
KDDI

KDDIは2020年8月にKDDI版ジョブ型人事制度を導入しました。新卒社員の一律の初任給制度を撤廃し、能力に応じた給与体系の導入を始めました。
ここでは職務領域を明確化し、働いた時間ではなく成果や挑戦を評価し、処遇に反映して人財を育成することが目的とされています。時間や場所にとらわれずに働けることを目指し、ジョブ型雇用を導入しました。
特徴は、ある程度大きなくくりで専門性を高められるようにしたことです。そうすることで、人材の固着化を防ぎながら幅広い人材を育成できるようになります。また、専門性だけでなく「人間力」も評価するという点も特徴です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回はジョブ型雇用についてそのメリットやデメリット、導入企業の実例を紹介しました。従来のメンバーシップ型雇用に比べ、ジョブ型雇用の導入は難易度が高く、企業側へのデメリットもあります。しかしテレワークの必要性が高まっている今、一人ひとりが主体的に仕事をこなすことができるジョブ型雇用は会社の業績改善につながるのではないでしょうか。
【関連記事】
人事評価コンサルティング会社15選!サービス内容、費用などを徹底比較します。
【最新版】人事評価サービスおすすめ17選!機能や価格で徹底比較!
ヒエラルキー型組織とは?ホラクラシー型組織との違いなどを説明します。
マトリクス組織をわかりやすく解説!特徴、メリット、デメリット、事例などをご紹介!
MBO(目標管理制度)とは?OKRとの違い、メリット、課題、効果的な活用方法
【事例あり】アルムナイ制度とは?メリット、デメリットなどを徹底解説
複線型人事制度とは?メリット・デメリット、事例や導入企業を詳しく解説します。
人事評価制度コンサルティングならお任せください

✓広告業界最大手グループのネット広告代理店等、50社以上との取引実績あり
✓契約継続率90%以上を誇る高品質サービス
✓月額200,000円~の圧倒的コストパフォーマンスを実現
✓調査から制度検討、シュミレーション、運用までトータルでサポート
✓評価者研修、従業員に向けた説明会、評価シート作成、1on1面談コンサルティング等も実施
✓少数精鋭だからこそ実現出来る、柔軟なサービス設計・ご対応
▼サービスに関するお問い合わせはこちらから

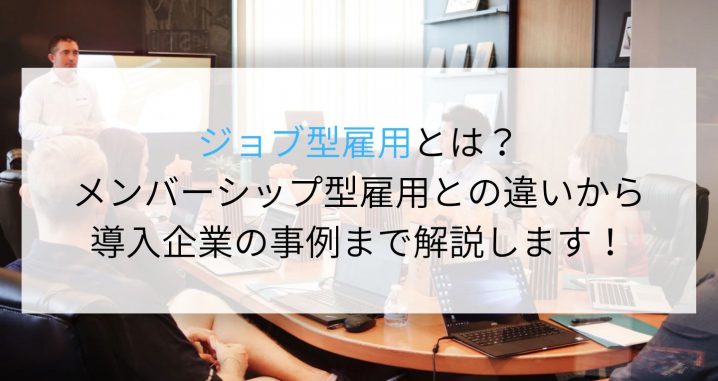



サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg)

